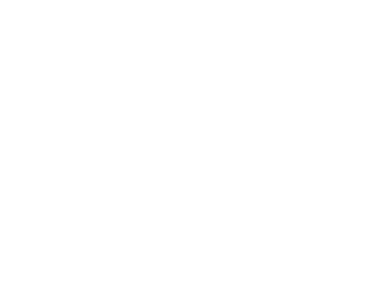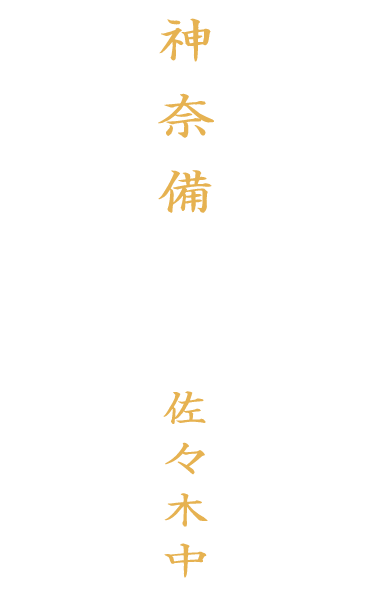
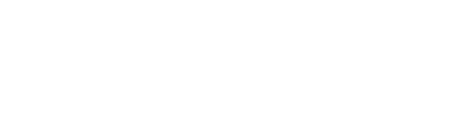
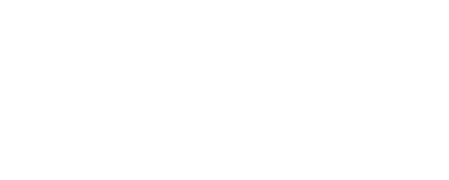 甘やかなやまとの女ことばの口語をつらねて行われる過去現在にわたる「国家神道」の徹底的批判の果てに、崇神天皇の和歌から神楽・催馬楽までを自在に引用する上代文学を極め尽くした新たな魔術的な文体を駆使しつつ、「この列島の文学」の絶対的に肯定する。強烈な「渡来する日本語」の冒険。
甘やかなやまとの女ことばの口語をつらねて行われる過去現在にわたる「国家神道」の徹底的批判の果てに、崇神天皇の和歌から神楽・催馬楽までを自在に引用する上代文学を極め尽くした新たな魔術的な文体を駆使しつつ、「この列島の文学」の絶対的に肯定する。強烈な「渡来する日本語」の冒険。かみさまがあなたを呼んでいるわ。聞こえたの。はっきりと。今すぐここに来て。きっと道がひらけると思う。
託宣だった。とおくかすれて、声はこのひとつ身を一瞬でつらぬいた。痺れた。四肢はきしみながらのろのろとうっそりと立ち上がって、けだるい嚇怒とやさぐれた思慕でびっしょり濡れたそのまま、旅支度をはじめるしかない。浄めの旅の。その奥の、奥からの、づづくろい骨や血や肉のくらいかさなりが、うごめきが、急に重く、きたなくなって、けがれになった。美咲が、けがれにした。なぜ、こんなに、生ぐさいのだろう。なぜ、このような、腐れていくものが、あせ染みしたうす皮いちまいにつつまれ、つまっているのだろう。人のなりをして、人づらさらして。その身を、ひととき、つくろわなければならない。手元のスマートフォンをみると、着信は二〇一三年四月四日一〇時三三分になっていた。
一二時二七分品川発のぞみ三四三号に乗り込んで、きづくと目をかたく閉じていた。つかれはひりひり痛がゆくて、あまくならない。睡りになだれて、くれない。目と頭蓋のなかでただただ凝って、酸をたらしたような沁みるいたさだけがふるふる対流して、果てしもないようになった。不眠とつれあって、ながい。昨日今日のことではない。が、いやまして睡りがひらたく、あさくなったのは、美由と逢ってからではないか。それすら、もう定かではなかった。(...

2015年2月24日刊行
佐々木 中 『神奈備』
河出書房新社 ▷www.kawade.co.jp
定価:1,944円 本体価格:1,800円
四六判 上製カバー装 148頁
978-4-309-02364-9 C0093